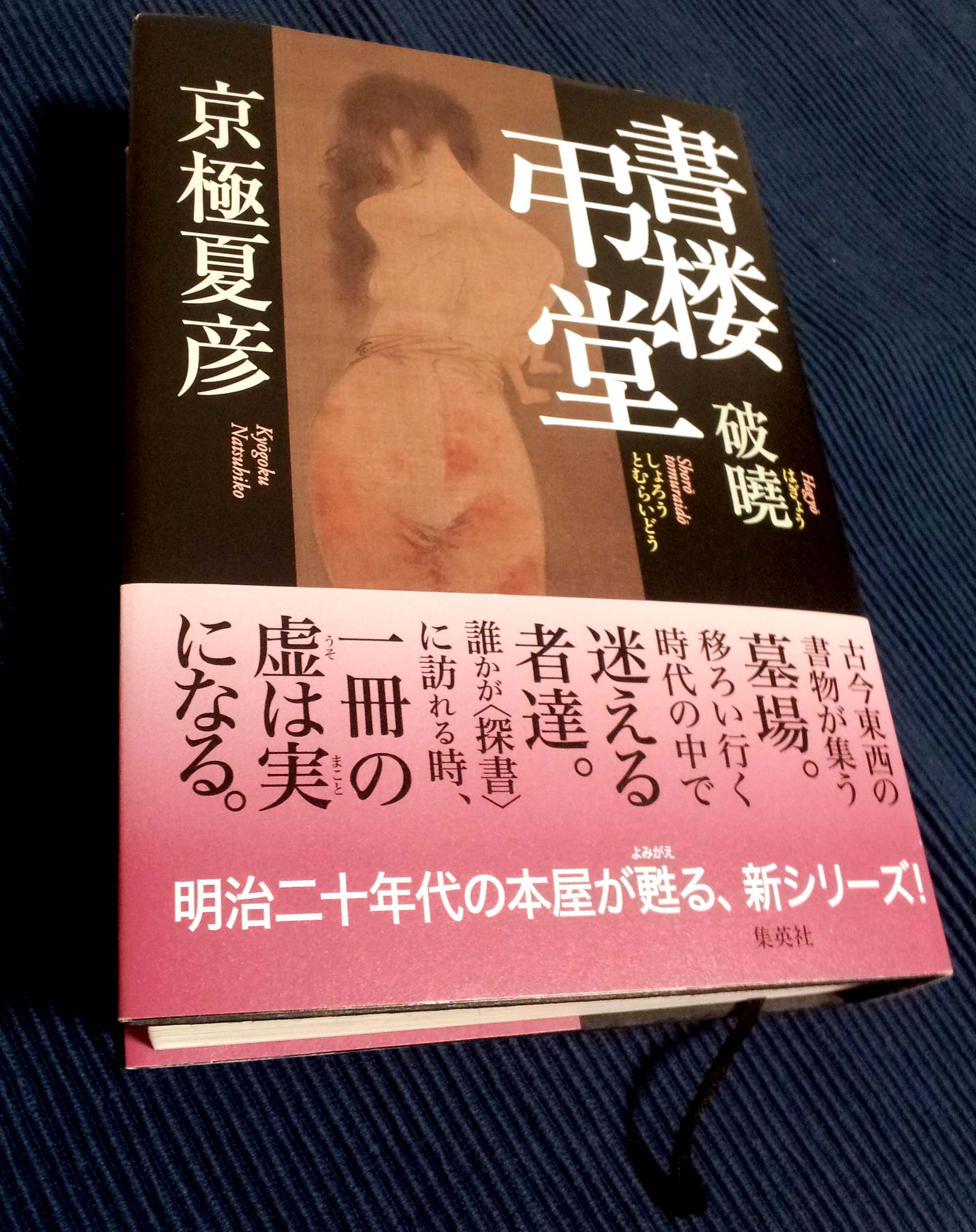ときは明治維新から20年後。舞台は、東京近郊にある怪しさ満点の古書店“弔堂”。
主人公は、ある日を境にその店へ通うことになる元士族で妻子持ちの中年ニート・高遠。
元僧侶の店主は、店にある書物を処方することで、客の悩み事に一筋の光をあてる。
たとえるなら古書店で行われる不定愁訴外来といったところ。
さらに来る客はみなみな実際に歴史に名を残す傑物ばかりで、
読み進むうちに次は誰が登場(来店)するのか、ちょっとした楽しみになっていく。
猿まわし役の高遠も、それらの処方に関わっていくうち、病んでいた心に少しづつ変化が芽生え…。
これまでの百鬼夜行(京極堂)シリーズに似ているようで、それでもまったく違うような、
いわゆる裏と表、陰と陽ともいえる構成が、大変おもしろい。
古書店“弔堂”と古本屋“京極堂”、白装束と黒装束、元僧侶と兼業神主(陰陽師)。
書物を処方し患者を祝う弔堂店主と、憑物落としで依頼者を呪う京極堂店主。
変わりゆく世についていけない高遠彬と、世間と折り合いを付けられない“うつ病”の関口巽。
当てはめていけばいくほど対照的にみえる舞台と役者たち。
ただ、百鬼夜行(京極堂)シリーズに比べ小難しくなく、わりと動きの少ない自然な話の運び方は、
初めて京極作品を手にする方にとって馴染みやすく、
一方、同シリーズや後巷説シリーズをこよなく愛する方にとっても
随所にリンクが貼られてあって、大変楽しめる作品になっている。
また、他の京極作品の例に漏れず、立て板に水のごとく展開する会話文はさずがの一言。
思わず声に出して読みたくなるほどの流暢な言葉のやりとりは、
テンポよく読み進むためのエッセンスとなって、ぐいぐい読み手をその世界へのめり込ませていく。
ラストはなんだか続くような終わり方でもあり、高遠の行く末も気になるところ。
早く次巻を手にしたいと、久しぶりに思わせてくれた嬉しい一冊だった。